父を亡くしてから1ヶ月の間に行った手続きのうち、この記事では、STEP1・2にあたる
「死亡診断書」と「葬儀会社への連絡」について、実際にやったことを詳しく書いています。
まずはこの書類がどんな場面で必要になるか整理しておきますね。
死亡診断書は臨終を確認した医師が作成してくれる書類となります。動揺しましたが、とても重要な書類なので、しっかり分けて保管して持ち帰りました。
死亡診断書が手書きの病院はまだまだ多いと思いますので、受け取る側も氏名が合っているかなど最低限確認の上、受け取れるようにしましょう。
ステップ1:死亡診断書を受け取る(当日)
- 確実に受け取ったか
- 他の書類と分けて保管したか
ステップ2:葬儀屋さんへ連絡(当日)
- 葬儀会社の連絡先を把握しているか
- 予定の斎場を間違えず伝えたか
死亡診断書の役目
死亡診断書の原本は役所に提出する死亡届の添付書類となりますので、手元には残りません。
このほかに生命保険請求時、銀行口座解約時などの添付書類としても使うため、コピーを取っておくことが重要となります。
ご自身でコピーを取ってももちろん良いですが、葬儀会社さんとやり取りする中で死亡診断書の用途やコピーの必要性を説明してくれて、用意してくれる場合もあります。
※私達の場合は葬儀会社さんがやってくださいました。
葬儀会社さんへの連絡
亡くなったのは午前1時頃でしたが、朝まで病院にいる訳にもいきませんでしたので、退院の準備も進めなくてはなりません。
父の移動のために母が葬儀会社へ連絡を取った時のことです。移動そのものはスムーズにできたのですが、予定していた斎場に到着していませんでした。この時に連絡先を取り違えてしまい、父が予定と違う斎場に移動していることが分かりました。
改めて移動となり、その分の費用もかかりました。申し訳ない気持ちになったのと同時に動揺の中では普段あり得ないことも起こると痛感しました。
葬儀会社さんの連絡を携帯に登録するのが無難かと思いますが、紙にメモして持っておいても良かったかなと感じました。
まとめ
死亡診断書の受け取りと葬儀会社への連絡は、亡くなった直後に直面する最初の大きなステップです。特にこの時期は悲しみと動揺が最も大きく、冷静な判断が難しくなりがちです。
だからこそ、
- 死亡診断書はコピーが必要と知っておく
- 葬儀会社の連絡先は事前に確認する
といった「ちょっとした準備」が、後々の安心につながると感じました。
同じ状況に直面された方や準備を考えている方に、少しでも参考になれば幸いです。
この記事は「父が亡くなってから1ヶ月でやった手続き」シリーズの一部です。
次のステップはこちら:
家族が亡くなった後の手続き③|家族葬の流れと費用感【我が家の体験】
シリーズ全体の手続きをまとめた記事はこちら:
父が亡くなった後の手続きまとめ(ステップ①~⑦)
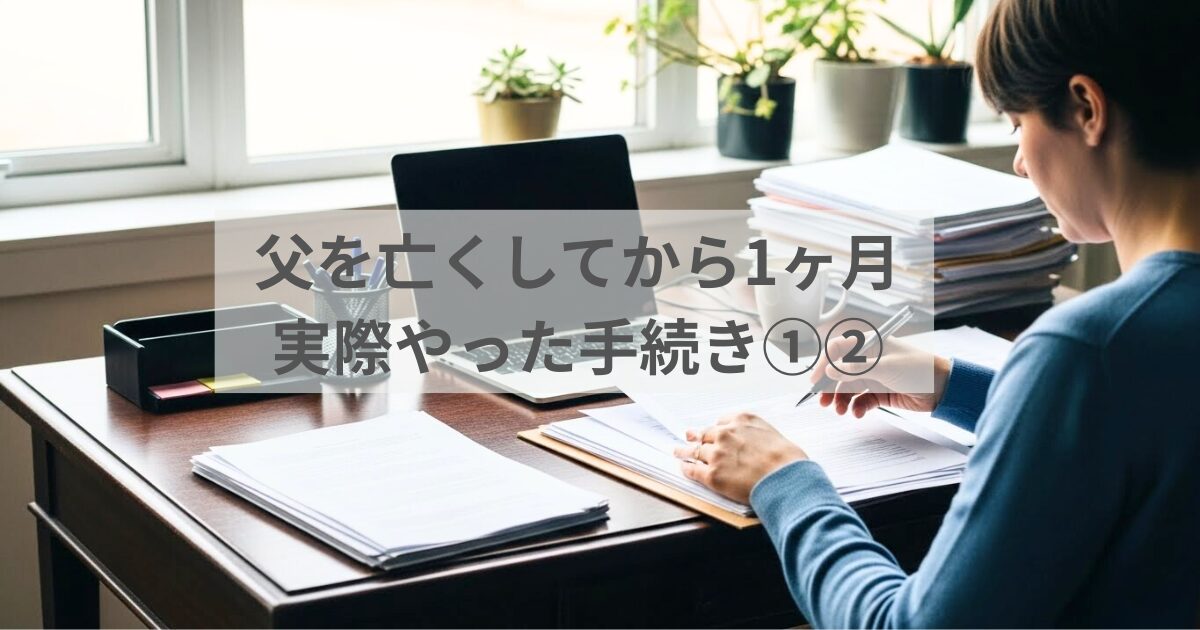


コメント