父が亡くなってからの最初の1ヶ月で、実際に私たち家族が進めた手続きを、チェックリスト形式でまとめました。
葬儀の準備と並行して進める必要があり、特に亡くなってからの1週間は、時間に追われながら動いていた記憶があります。
父が亡くなってから1年が経ち、当時を振り返りながら、体験を交えて整理しています。
同じような状況に直面されている方が少しでも迷わず進められる一助になれば幸いです。
ステップ1:死亡診断書を受け取る(当日)
- 確実に受け取ったか
- 他の書類と分けて保管したか
👉️死亡届、火葬許可、生命保険の申請などに必要な重要書類です。
実際の体験
・死亡確認後、医師が作成してくれた書類を当日受け取りました。
・動揺の中でしたが、とても重要な書類なので、しっかり分けて保管しました。
詳しくはこちら:
父を亡くしてから1か月間でやった手続き①②|死亡診断書の使い道と注意点まとめ
ステップ2:葬儀屋さんへ連絡(当日)
- 葬儀会社の連絡先を把握しているか
- 予定の斎場を間違えず伝えたか
👉️動揺の中で伝達ミスが起きやすいので要注意。
実際の体験
・母が連絡先を取り違えてしまい、父が家族の想定と違う斎場に移動してしまいました。
・改めて移動となり、その分の費用も発生。動揺の中では普段あり得ないことも起こると痛感しました。
詳しくはこちら:
父を亡くしてから1か月間でやった手続き①②|死亡診断書の使い道と注意点まとめ
ステップ3:葬儀内容を決める(翌日)
- 家族内で葬儀の範囲や喪主を決めたか
- 死亡届、火葬許可証は手配できているか(死亡届は7日以内に手続き)
👉️葬儀は手続きと同時に決めることがたくさんあります(日程、様式、火葬場、棺など)。
実際の体験
・父の希望通り「家族葬」と決めていました。追加提案は丁寧にお断りしました。
・役所への死亡届の提出、火葬許可証の申請は葬儀屋さんに代行してもらうことも可能です。
・火葬場のある自治体に故人あるいは喪主の住民登録があると、火葬料が免除されるケースもあります。
詳しくはこちら:
父が亡くなってから1ヶ月でやった手続き③|家族葬を選んだ理由と実際の流れ、概算費用はどれくらい?
ステップ4:年金事務所への連絡(1週間目)
- 年金事務所の連絡先は把握しているか
- 国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内
👉️自動動停止しないので、受給停止の手続きが必要です。
実際の体験
・この手続きは期限が短く、まず年金事務所に電話して必要書類を郵送してもらいました。
詳しくはこちら:
父が亡くなったら年金はどうなる?|年金受給停止の手続きと年金事務所への連絡【体験④⑤】
ステップ5:行政サービスを活用(2週間目)
- 自治体に一括申請窓口があるか確認したか
👉️窓口があると書類集めの負担が軽くなります。(おくやみ窓口等で検索)
実際の体験
・提出する書類が思ったよりありました。この窓口はwebや電話で予約すると今後必要な手続きを調べてくれます。書類は郵送でも受け取りできます。
・国民健康保険加入の場合、自治体から葬祭費の給付が受けられます。このような知らないと見落としそうな書類も届きました。
(支給額は5~7万円の範囲が多いようです、喪主に方に給付されます)
詳しくはこちら:
父が亡くなったら年金はどうなる?|年金受給停止の手続きと年金事務所への連絡【体験④⑤】
ステップ6:司法書士さんに相談(3週間目)
- 相続する土地や家があるか確認したか
- 預貯金や車などの遺産はあるか
👉️相続登記は2024年4月1日より義務化されています。
👉️預貯金を分割するといった際も相続人全員の合意が必要です。
実際の体験
・法定相続人や遺産分割の内容を整理するだけでも時間がかかりました。
・2つの金融機関で手続きしましたが、相続関係説明図と遺産分割協議書を用意していたので負担は軽くスムーズに進みました。
・相談~書類作成~手続き完了まで3週間程度、費用は約13万円、専門職を頼って正解でした。
詳しくはこちら:
父が亡くなってから1ヶ月でやった手続き⑥|司法書士さんへの相談で相続登記や遺産分割をスムーズに
ステップ7:生命保険の受け取り申請(4週間目)
- 契約先や保険証券を確認したか
👉️受け取ったお金はまず「守る」意識を大切に。
実際の体験
・保険会社に連絡すると申請書類が郵送されてきます。必要書類を揃えて返送する流れです。(申請書と死亡診断書のコピーを返送しました)
・申請期限は3年以内が一般的ですが、遺してくれた大切なお金ですので忘れないよう早めに申請して受け取りましょう。(投函して10日程度で入金がありました)
詳しくはこちら:
父が亡くなってから1ヶ月でやった手続き⑦|生命保険の受け取り申請とお金を守る意識
まとめ
悲しくても多くの手続きを同時に進めなければなりません。
私たちは家族で分担したり、専門職の方に頼ってなんとか乗り越えることができたと思っています。
チェックリスト形式にまとめましたので、まず全体を把握し、そのうえで必要な部分を一つひとつ進めていただければと思います。もし同じような状況にある方に、この記事が少しでも役立てば幸いです。
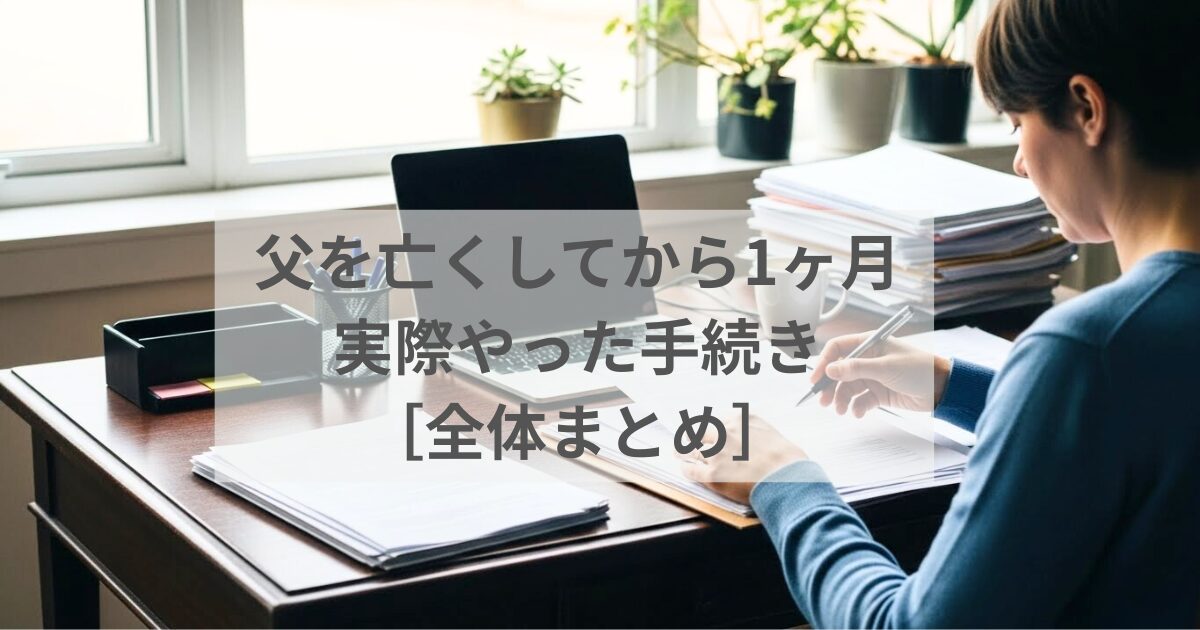

コメント